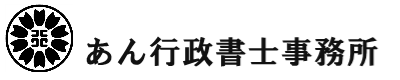遺言の形式を整えよう!
遺言の作成ルールは、民法で決められています。
形式的に整っていることが必要です。
遺言の本文
1 本文は、全部自分でボールペンや万年筆・毛筆など消えない筆記用具で書く
法務局に遺言書を預ける「遺言書保管制度」を利用する場合、
用紙は、模様がないA4サイズの紙で、余白を上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートル以上取る。
2 日付を具体的に書く。
例えば、「令和7年7月7日」と書く。
3 自分の名前を書く(戸籍のとおり書く)
4 名前の隣に印を押す(実印で押印し印鑑証明を添付するとベスト)
遺言の目録
1 パソコンで作成した一覧や預金通帳のコピーを使用できる。(片面のみ使用することを推奨)
法務局に遺言書を預ける「遺言書保管制度」を利用する場合、
用紙は、模様がないA4サイズの紙で、余白を上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートル以上取る。
2 目録の左上に、「別紙1」「別紙2」のように表示する。
3 目録の右下に 自分の名前を書く(戸籍のとおり書く)
4 名前の隣に印を押す(実印で印鑑証明を添付するとベスト)
遺言の製本
1 目録を含めて2枚以上あるとき製本します。
2 右下にページを付ける
例えば、3ページあるとき「1/3」「2/3」「3/3」と表示します。
「1/3」は、3ページあるうち1ページ目であることを意味しています。
3 左端2か所にホチキス止めします。
この時、ホチキス止めの部分で紙を折り返した時に文字がかからないように注意しましょう。
4 契印(割印)を本文で使用した印鑑を使って押印します。
1枚目をホチキスのところで折り返し1枚目と2枚目に係るように押印します。
2枚目と3枚目も同じようにします。以下、同様に最期のページまで繰り返します。
※ 法務局に遺言書を預ける「遺言書保管制度」を利用する場合、製本はしません。
禁止事項
1 複数人での署名押印した遺言書は無効です。
誰の意思なのかわからないので無効になります。
2 ビデオや録音のみで遺す遺言は無効です。
3 パソコンで作成プリントした遺言は無効です。
4 全文自分で書いた遺言のコピーを原本とした遺言は無効です。
何らかの理由で文字を書けない方
公正証書遺言で遺言を作成ることが出来ます。
遺言者が公証人に対し口述又は筆談によって作成することが出来ます。
(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(共同遺言の禁止)
第975条 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。
遺言の内容
財産分割や身分に関することなど(法定遺言事項)
何をどのくらい誰に相続させる(遺贈する)のかなど具体的に書く。
法的に効力はないが、遺言書を作った理由や家族への感謝のメッセージなど(付言事項)
法定遺言事項と整合性を図り、相続人のみんなが幸せになるように書く。
専門家の意見を聞く
相続人多数の場合。財産が多い場合。その他複雑な場合は、専門家の意見を聞いてください。